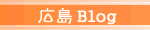児童文学が描く母親の愛
2009 年 2 月 9 日
随分前の話になりますが、6年生の女子クラスを担当していたときのことです。「これは思春期間近の女の子によさそうだな」と思って、子どもたちに紹介した本がありました。「銀の馬車」という書名のその本は、母親に反発する女の子が、やがて自分に向けられた母親の深い愛情に気づく物語です。
子ども時代にご経験ありませんか?「あなたはお姉さんでしょ。しっかりしてくれないと困るわ」「弟の面倒をもっとみてくれなきゃ」「私の気持ちを、どうしてわかってくれないの?」など、説教じみたことを言われるのが疎ましく、母親に反発心を覚えたことは?
2~3週間後、ある女の子が報告してくれました。「先生、この間教えてくれた本、あれで泣いて、泣いて・・・・・・」 筆者はすっかりうれしくなり、「えっ、もう読んだの?あの話、感動するよね」と答えました。すると、すかさず「ううん、違うよ。読んだのはおかあさん」と切り返されました。 なんと、感動して泣いたのはおかあさんでした。
当時は、女の子の成長という視点からのみ、その本を読んでいたような気がします。しかし、ストレスを溜めながら子育てをしている妻を見、また、自分自身も子育て上の様々な悩みを経験してきた今は、親の視点からもこの本のすばらしさを理解しているように思います。この本を読んで泣けてくるのは、子どもではなくむしろおかあさんなのです。
本の内容をもう少しご説明しましょう。「銀の馬車」は、アメリカの児童文学作品で、両親の離婚という困難を乗り越えていく少女の物語です。離婚後、娘二人の面倒は母親がみることになりました。そこで、母親は夏休みの間に正式な職を得るための資格をとろうと、学校に通うことを決心します。その間、姉妹は山の中で一人暮らしをする父方の祖母に預けられることになります。この祖母との暮らしを通じて、姉妹が大きく成長するというのが、この話のおおよその内容です。
主人公の女の子は、自分にばかり辛くあたり、ヒステリックに叱ってくる母親を恨んでいました。対照的に、妹は天真爛漫で誰にもかわいがられます。「どうして私ばかり・・・・・・」と、母親が恨めしく、一悶着あるたびに「ああ、何でおとうさんは私を引き取ってくれなかったのかしら。おとうさんなら優しいし、仲良く暮らせるのに」と、おとうさんと二人で暮らせる日が訪れることを夢見るのでした。
そんな女の子が、妹とともに祖母の家で暮らす体験を通じて、少しずつ母親の自分に対する深い愛情に気づき始めます。物わかりがよくて優しい父親が、本当は愛してくれていたわけではなく、また、自分本位で責任感に欠ける人間であることにも気づいていきます。そうした父親の性格が離婚の原因であり、母親は「自分が子どもたちを育てなければ」という強い責任感から、余裕を失っていたのです。自分に厳しかったのも、「上の子はしっかりしてくれているから、何とかやっていけるだろう」という、信頼の気持ちがあったからでした。
この作品で重要な脇役を担っているのは、おばあさんです。離婚後間もないというのに、新しい家族を連れてくる無神経な息子(姉妹の父親)に対して、静かな、抑制された怒りを向けるシーンが印象に残ります。また、経済的な自立を必死になって模索する母親や、父親を失った孫たちに深い愛情を注ぐこの人物の存在で、暗くなりがちなストーリーに希望をもたせる効果が生まれているように思います。
児童文学は、事実よりも心に響くことがあります。また、どこにでもありそうなことを、実にリアルに描いてくれます。ご紹介した作品も、その一つです。この作品を知っていたことがもとで、あるとき、思わぬドラマが起こりました。次回は、そのことについて書いてみます。
「銀の馬車」 キャロル・S・アドラー作 金の星社(フォア文庫からも出版)
 このページは
このページは