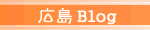学力形成の基盤は家庭の豊かな会話にある その2
2014 年 7 月 28 日
前回は、子どもが家庭でどのような会話をして育ったかが、知的能力の形成に多大な影響を及ぼすということを踏まえ、会話を成立させるうえで中心となる「聞くこと」「話すこと」の役割と重要性について考えてみました。
家庭で慣れ親しんだ会話のスタイルに優劣はありません。ただし、教育の場で用いられる言葉と隔たりが大きければ、子どもにとってある種のハンディになってしまいます。込み入った思いや、複雑な事象についてのやり取りを可能にする話しかたを耳にしたり身につけたりする機会に恵まれていれば、子どもは自然とそういう会話環境に適応していきます。その意味において、会話環境は子どもの知的成長にとって大変重要なものなんですね。
さて、小学校という正式な学習の場に参入した子どもたちは、いよいよ「読み・書き」の学習を開始し、少しずつ学問の世界へと足を踏み入れていきます。
 まず、「読むこと」から子どもたちの学習のステップをみていきましょう。ただし、読みの力をつけるプロセス、特に音読についてはすでに何回もお伝えしています。そこで、今回は読みの力を養ううえで見落とされがちなこと、気をつけたいことに着目して書いてみようと思います。
まず、「読むこと」から子どもたちの学習のステップをみていきましょう。ただし、読みの力をつけるプロセス、特に音読についてはすでに何回もお伝えしています。そこで、今回は読みの力を養ううえで見落とされがちなこと、気をつけたいことに着目して書いてみようと思います。
当然ですが、「読む」ためには文字を知らなければなりません。小学校に入ると、文字を一から学習していきますが、大半の子どもは就学前にひらがな71文字のうちの大半を読めるようになっていると言われます。なかには、漢字の読み書きもかなりできるようになった子どももいます。
では、先行体験は有利に作用するのでしょうか。そう思う人が多いから、早期教育が盛んなのでしょう。しかし、実際には逆効果をもたらすこともあるようです。というのは、先行体験が「親に要請されたから」「親が喜んでくれるから」といった受動的な理由によるものである場合、かけた時間や労力に見合うほど成果につながりません。むしろ、後から学び始めた子どものほうが、「文字って便利だな」「おかあさんに手紙が書ける!」といったように、文字の機能性に着目し、それを文字学習への意欲につなげていくため、進歩が早いと言われます。そうなると、小学校入学当初の差は、1年余りであらかたなくなってしまいます。
文字の習得がある程度進むと、子どもは簡単な文が読めるようになり、さらには短い文章も読めるようになっていきます。こうした学習のプロセスでの「読み」は、音読によるものです。詳しくは書きませんが、音読を十分に経て自然と黙読へ移行するのが自然な流れです。
一般に、黙読は2年生の前半~中盤頃可能になると言われます。文字列を声に出して読みながら、自分の耳で既知の音声言語(話し言葉)と照合していくことの繰り返しで、子どもは徐々に文字列を視覚でとらえた瞬間に、言葉のまとまりを仕分けられるようになります。それに連れて読みは正確で速くなっていきます。そして、やがて文字情報を視覚でとらえると同時に、それに対応する音声の言葉を脳内でイメージできるようになります。これを音韻表象と言いますが、音韻表象ができることで、子どもは声に出して文を読まなくても文の意味を理解できる(黙読できる)ようになります。
黙読は、読みの負担を著しく軽減します。読みの負担が少なくなると、子どもは自然と本を読むことへの意欲を高めます。そうして、読書活動がいよいよ本格的なものになっていきます。
高学年になった子どもの読解力不足を心配する声をよく耳にします。これは子どもの能力の問題ではなく、黙読への移行プロセス、とりわけ音読の不足がおおもとの原因で、そのために読みが不正確で遅いなどの問題が生じたためではないかと思われます。上手に滑らかに文章を読めないと、誰でも本を読むのが億劫になるものです。決して本嫌いだから読まないのではありません。
子どもが本の世界に入り込み、夢中になるのは黙読が安定軌道に乗る3年生頃からです。それから1~2年間のうちに、みるみる子どもは語彙を増やし、読みのレベルアップ、思考のレベルアップを果たしていきます。そうしたプロセスを経験していれば、読みの習熟不足、読解力不足の問題は解消できます。
こうした読みの習熟、思考のレベルアップを果たすうえでの土台となるのは豊かな会話を通して築いた「聞くこと」「話すこと」の力です。読みの能力を身につけるには、文字列を声に出して読み、その声を耳でとらえ、既知の音声言語との照合を絶え間なく繰り返さねばなりません。この作業は、話し言葉の使用状況が豊かであればあるほどスムーズに行えるでしょう。
 次に、「書くこと」について考えてみましょう。書くことについても、小学校入学の時点で自分の名前を書ける子どもはたくさんいますし、簡単な文を既に書けるようになっている子どもも少なくないと思います。
次に、「書くこと」について考えてみましょう。書くことについても、小学校入学の時点で自分の名前を書ける子どもはたくさんいますし、簡単な文を既に書けるようになっている子どもも少なくないと思います。
ただ、書くことは読むことよりも難しい要素があります。まず、小学校に入学したての子どもは指の筋肉が未発達なため、書くという作業自体がままなりません。それに加え、自分の考えたことを頭に思いめぐらせながら文にすることは、小学校に入学したての子どもにとっては至難の業です。第一、「誰が読むのか」を想定しながら書くのは大変高度な知的作業です。
そのため、小学校1年生でまともな作文を書ける子どもはごくわずかだと言われます。これは、2年生になってもそう変わりません。学者の調査によると、1年生の作文の総文字量と、2年生のそれとを比較したら、大きな違いが見られませんでした。この時期、「うちの子は書くのが苦手」というおかあさんが多いようですが、実は「書けなくて当たり前」なんですね。
ただし、日記を日課として定着させたり、親子の交換日記を行ったりするなど、書くということを子どもが継続的に行うようになった家庭では、目に見えない変化が着々と進んでいきます。文字量こそ急激には増えないものの、書いている内容が徐々に進歩していくのです。
そうして、目に見える大きな変化が3年生の頃やってきます。いつの間にか、子どもはかなり長い文章を、それもある程度構想立てて書けるようになっていくのです。1~2年生のころまで、書くことに取り組んでいた子どもも、書くことを疎んじていた子どもも、同じように書く能力が身についていないように見えたのが、ここにきて一気に差が表面化するのです。そして、ここで明らかになった差は、放っておくとどんどん広がっていきます。
この「書くこと」に関しても、土台となるのは、家庭で磨いてきた会話の力です。自分の考えをまとめて書くには、まず自分の頭のなかにある考えを思考のまな板の上に載せ、それを順序立てて言葉で組み立てていく必要があります。これは、会話のときと同じです。書く場合、それに書こうとする内容のコマンドを信号によって運動野を経由して筋肉運動に変える作業を加えることになります。発信したい情報をまとめるまでは基本的には同じですから、家庭で豊かな会話生活を経験していることは立派なアドバンテージになるでしょう。
以上のように、「聞く」「話す」「読む」「書く」は、すべて言葉を介した頭脳作業であり、互いに密接なつながりをもっています。子どもが成長し、学年が上がるにつれて「今更ついた差はどうしようもない」と、親があきらめてしまうケースがありますが、どのような年齢、学年であれ、「聞く」「話す」「読む」「書く」ことに関する力は、やったらやっただけのことがあるものです。
脳は、繰り返し入力された情報に順応していきます。書くことを繰り返していれば、必ず書くことを快適にやれる脳に少しずつ近づいていきます。小学生の場合、何年生でも繰り返し努力すれば必ず進歩していきます。筆者自身、このブログ記事を450回以上書いてきましたが、そのせいか、今ではA4の紙に2~3ページ程度の原稿は苦ではなくなりました。「繰り返し」と「努力」は偉大なものだとつくづく思います。
最後に。家庭での会話のもつ重要性は、子どもが小学校に入学した後も、上の学年になってからも変わることはありません。毎日の会話を通して、子どもは相手の意図や気持ちを深く理解したり、自分の思いや伝えたいことを相手の誤解を受けないよう伝えたりする能力を磨いていく必要があります。また、家庭での親子の会話の際、お子さんが学校での様々な学習体験を通して成長しつつあることを実感されることも少なくないと思います。つまり、家庭の会話と学校での学習成果は、相互補完しながら子どもの知的発達を後押ししていくのですね。
親にはやらねばならないことがたくさんあります。しかし、そういうあわただしい生活のなかでも、毎日少しでも結構ですから、楽しい親子の会話の時間を設けていただきたいと思います。それは、子どもの内面の成長にとってかけがえのない栄養になるでしょう。受験生活が始まると、「おしゃべりより勉強!」といった発想になりがちですが、小学生の受験においては、親子の会話も受験対策の一環と言ってよいほど重要なものです。
 このページは
このページは