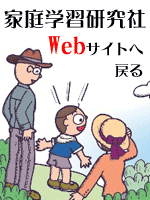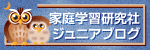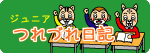2023 年 6 月 13 日
ブログをお休みしてだいぶ経ちました。10数年続けてきて、中学受験生の保護者以外の方々も多数お読みくださっていることを知っていましたので、心苦しく思っています。ブログ休止の理由ですが、一定の年齢に達して仕事をする日を減らしているなか、今年はさらに担当分野に変動があり、長い文章を吟味して書く時間がなくなりました。
今回は久々の記事ですが、よくお読みいただいているような家庭教育に関するものではなく、催しの案内です。なぜかと申しますと、これからご案内する催しは筆者自身が進行役を務めますので、ぜひ聞きに来ていただけたらと思ってキーボードに向かったしだいです。
弊社イベント 「今こそ、未来的視点に立つ中学受験を!」 6/23・30
☆お申し込みはこちら!専用申込フォーム
この催しの実施にあたり、広島最難関の私学として知られる広島学院さんにお声がけし、現在の中学受験の実態はどうなのか、生徒の学力水準に変化があるのかどうか、そのあたりの実際のところをお聞きしようと思います。
中学受験が盛んな頃は、合格を得るために相当ハードな受験対策が当たり前のように行われていました。基礎基本を重視する弊社はそのあおりを受け、合格を得るのに苦戦を強いられていた時期もあります。しかしながら、「家庭学習研究社の方針に沿った勉強が、中高一貫校に入ってから生かされています!」という熱い応援をくださる保護者の方々が多数おられ、勇気をいただいたことを懐かしく思い出します。それ以後、合格のも実績もいつの間にか回復して現在に至っています。本催しを通じて、このことの意味を保護者の方々とともに考えてみたいと思います。
いっぽう、時代は大きく変わりつつあります。IT社会が進行するなか、同じように立派な大学を出ても、自らの能力をどう伸ばしたかにより、「AIに使われる人間、AIを活用できる人間」などのように人生の立ち位置が変わってしまうおそれが生まれています。もはや、学歴だけで食べていける時代ではないことを、保護者の方々はよくご存じのことでしょう。学歴を真に生かせる人間になるか、それとも生かせない人間になってしまうか。その分かれ目として見逃せないのが、中学受験に備えた学習のありかたです。家庭学習研究社の推進する受験対策は今のままで通用するのか、様々な観点から検証してみようと思います。
こうしたテーマについて考えていくにあたっては、最難関の中高一貫校で学ぶ生徒さんの様子は随分と参考になるでしょう。また、私学が世の中の変化に合わせ、どのような思いで教育に当たっておられるのかをお聞きすることも大いに参考になるでしょう。中高一貫校で自らの知性を磨き、社会の一線で活躍できる人間に成長している生徒さんに共通する特徴についても知りたいところです。さらには、中高一貫校の教育環境で学力の飛躍を遂げるために、小学校時代にどのような準備をしておけばよいのかについても、知りたい保護者は多数おられることでしょう。これらのテーマについての知見を得るうえで、広島学院さんは最もふさわしい中高一貫校であると考え、広島学院の先生がたをお招きしました。
筆者は、中学受験準備期(児童期後半)の親の関わりこそが子どもの人生の歩みを決定づける最重要要素だと思っています。何しろ、この頃の家庭教育や生活のありかたによって子どもの性格や行動様式、ものの考えかたや取り組みなどの個性が定まるのですから。これについては時間を十分に確保し、広島学院の先生に見解をお聞かせいただこうと思っています。なお、本催しは佐伯区民文化センターと西区民文化センターの二箇所で実施しますが、先生のご都合に合わせ、校長先生もしくはベテランの先生にお話をいただくことになっています。
小学校を出たばかりの子どもが、中高一貫校に進学し、6年後にはいっぱしの青年となって大学へと進学していきます。受験準備期の重要性は既述の通りですが、親の目が行き届かなくなる中学高校生活の充実にとって「どのような学校に進学するか」も非常に重要なファクターとなるものです。どんな6年間を過ごすべきかについて、広島学院の先生がたのお話が参考になればうれしいです。
最後に、夏期講座の会員募集にあたり、弊社の校舎長から「家庭学習研究社の実践する学習指導」の特徴について保護者の方々にご説明いたします。これからお子さんが中学受験のための学習を開始されるご家庭はもとより、現在弊社の教室で受験勉強に取り組んでおられるお子さんの保護者の方々にとっても受験対策の根本事項をご確認いただける機会となります。
本催しが、お子さんの健全な成長を願っておられる保護者の参考になることを願っています。なお、この催しへの参加にあたっては、事前にお申し込みいただく必要があります。弊社ホームページの案内をお読みいただき、所定の手続きをお願いいたします(19日が締め切りです)。
☆お申し込みはこちら!専用申込フォーム
男子受験生の保護者だけでなく、女子受験生の保護者にも参考にしていただける催しです。ぜひお気軽に参加ください!
カテゴリー: 家庭学習研究社の特徴
2023 年 3 月 10 日
2023年度の講座が開講して約2週間が経過しました。新年度講座の始まりは、学習面での成長の契機にする絶好のチャンスです。「塾で今までよりも難しい勉強が始まるぞ!」という意識が、お子さんの勉強に向き合う姿勢ややる気に変化をもたらすからです。小学校においても、一つ上の学年への進級が控えていますから、お子さんは否が応でも「がんばらなきゃ!」と思っておられることでしょう。そういった気持ちを大いに刺激しつつ応援してあげていただきたいですね。
ところで、みなさんは「終わりよければすべてよし」という諺があるのをご存知だと思います。保護者におかれては、この言葉を心の隅において最後までお子さんの受験生活を見守り応援していただきたいですね。この諺を話題に取り上げたのは、入試結果がよければ、受験生活がどのようなものだったかは問題ではない」と言いたいからではありません。そうではなく、「いろいろと受験生活において困難やもどかし思いをすることがあったが、終わってみたら得るものが多々あった。挑戦してほんとうによかった!」と、心から思える受験を実現してくださいね」という筆者の思いをお伝えしたかったからです。
とは言え、今はまだ1年間の講座が始まったばかり。受験で最高の結果が得られるような、充実した受験生活の実現をどのご家庭においてもめざすべきでしょう。1年あれば、子どもは大きく変わります。どの保護者におかれても、お子さんには大きな期待や夢をおもちだと思います。それを現実のものにするうえでまずもって大切にしていただきたいのは、1年の学習がスタートした今という時期です。その意味において、先ほどの諺をもじった表現で恐縮ですが、筆者は「初めよければすべてよし」という考えも意識していただきたいですね。フレッシュな思いが溢れるスタート時にしっかりとした学習の流れを築けば、勉強に手応えが得られる、テストの成績が伴う、自信がつく、やる気がますます高まるといったように、好循環の連鎖が生まれるからです。繰り返します。スタートして間もない今の時期を大切に!
以上が今回のブログで保護者の方々にお伝えしたかったことです。しかし、もう一つお伝えしたいことがあります。それは、「お子さんの受験生活が有意義なものになり、学力が大きく伸びているような家庭に見られる共通点はどんなことか」ということです。無論、受験生活がうまくいく要因は数限りなくあるでしょう。ただし、いずれにしても言えるのは、「子ども任せの勉強や生活では成功できない」ということです。そこが高校や大学への受験と中学受験との最大の違いです。しかしながら、それでいて受験の主役は子ども自身です。親のサポートを受けながらも、入試が近づくにしたがって着実に自分自身の受験勉強へと子どもを成長させていくことが重要です。子どもを自律へと向かわせる親のサポート。これこそ、小学生の受験に求められるものだと思います。
たとえば、お子さんが受験生活で着実に成果をあげ、すばらしい学力の向上を果たしている家庭の保護者に見られる共通点をいくつかあげてみましょう。
~受験生活で成果をあげているお子さんの保護者の共通点~
1.わが子が今何を学んでいるのかを掌握している。
勉強するのは子ども自身です。しかし、小学生の場合、自分の取り組みに親が関心を示し、応援してくれるかどうかがやる気や取り組みに大きく影響します。また、わが子が今何を勉強しているのかを知らなければ、親としてタイムリーな励ましや助言はできません。塾でどんな授業を受け、家庭勉強としてやるべきことは何かを親も知っておかないと、子どもが成果のあがる勉強をしているかどうかを掌握できません。
2.子どもの勉強に深入りしない。さりとて子ども任せにも
しない。
4年生の段階では、家庭学習の管理や維持を子どもに委ねるのは難しいものです。そこで、取り組みをある程度手伝ったり(日課の助走部分を一緒にやるなど)、やり終えた課題の〇つけをしたりすることも保護者にお願いしています。しかしながら、大切なのはやがてはお子さんが自分でやれるようにするためのサポートであるということです。6年生になってからも勉強の割り振りや、どこまでやっておくかの判断を親がしてしまうと、自律性の高い学習へと移行するタイミングを失ってしまいます。子どものひとり立ちを意識し、徐々に手を放していくことを常に頭においてサポートしてあげてください。
3.生活全般の自律性を尊重する。自発的行動を評価軸に
据える。
自分のことを自分でする習慣や姿勢のないお子さんに、勉強の自立を果たすことなど到底無理というものです。生活面でも、「自分のことは自分でしよう」と伝え、何につけ、親に言われて嫌々やるのではなく、率先してやる態度を尊重してやりましょう。大人でもそうですが、よいことをしたときに、「これは自分からやったのだ」と思うと誇らしい気分になるものです。そういう行動を見たときには、タイミングよくほめてやりましょう。そういう経験をくり返した子どもは、段々と親に言われなくてもやるべきことを率先してやるようになっていきます。これがラストスパート時の伸びにつながります。
以上のような接しかたを上手にされている保護者のお子さんは、「授業」と「家庭学習」の連携がスムーズで、取り組んだことの成果も上がりますし、勉強の自立が少しずつ進んでいきますから、受験勉強が佳境に入る6年生の秋になったときの心配や負担がずいぶん軽減されるものです。お子さんの自立促進を意識しながらのサポートを心がけていただきたいですね。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
お子さんが勉強の要領をよくわかっていなかったり、保護者自身もどうサポートしてよいかわからなかったりする点がおありでしたら、遠慮なく担当者にご相談ください。
今回、もう一つお伝えしなければならないことがあります。この3月からの筆者の勤務日や時間が大きく変わり、ブログを書く時間が確保できなくなりました。今後はイベントなどの催しの企画実施、家庭教育に関わる相談への対応が筆者の主たる業務となりました。これまで、累計230万ビューを超える閲覧を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。ただし、ときどき時間が確保できたときには書くつもりでおります。ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
カテゴリー: ごあいさつ, アドバイス, 中学受験, 勉強の仕方, 子どもの自立, 家庭での教育, 家庭学習研究社の特徴, 家庭学習研究社の理念
2023 年 2 月 28 日
前回は、今年の弊社会員の公立一貫校への合格と進学の状況をご報告しました。そこで今回は、国・私立中学校への合格と進学の状況をご報告しようと思います。国立と私立を一括りにしたのは、公立一貫校の適性検査と異なり、どちらも学力試験による受験生の選別を基本にしているところによります。ご了承ください。なお、まだ進路については未確認の会員家庭が一定数あります。数字はあくまで参考程度に留めていただくようお願いいたします。
主要中学校の応募者数を見ると、男子の広島学院や修道が昨年比で若干持ち直し、女子のノートルダム清心や広島女学院は若干減少気味で、おおむね横ばい状態となっています。ともあれ、さっそく弊社会員の合格状況、進路選択状況をご紹介してみましょう。
2023 主な国・私立中学校の弊社会員合格者数・進学者数 (3/2現在)
|
中学校名
|
募集人数
|
弊社会員合格者
|
弊社会員進学者
|
|
広島学院中学校
|
私・男
|
184
|
57
|
45
|
|
修道中学校
|
私・男
|
276
|
147
|
83
|
|
広島城北中学校
|
私・男
|
200
|
139
|
36
|
|
崇徳中学校
|
私・男
|
100
|
5
|
3
|
|
ノートルダム清心中学校
|
私・女
|
約180
|
85
|
63
|
|
広島女学院中学校
|
私・女
|
約200
|
145
|
52
|
|
安田女子中学校
|
私・女
|
200
|
117
|
27
|
|
比治山女子中学校
|
私・女
|
90
|
21
|
4
|
|
AICJ中学校
|
私・共
|
140
|
男12・女13
|
男2・女2
|
|
広島なぎさ中学校
|
私・共
|
約200
|
男68・女38
|
男13・女7
|
|
近畿大学附属中学校
東広島校
|
私・共
|
140
|
男19・女19
|
男5・女3
|
|
広島大学附属中学校
|
国・共
|
120
|
男16・女11
|
男4・女9
|
|
広島大学附属東雲中学校
|
国・共
|
80
|
男8・女8
|
男5・女3
|
※2月24日現在、まだ進路選択が確認されていない会員が若干名います。
弊社の主要ターゲット校は広島学院、修道、ノートルダム清心、広島女学院の私学4校と、国立の広島大学附属中学校です。合格状況ですが、ノートルダム清心中の合格者が昨年比13名増加したことと、広島大学附属中の合格者数が昨年比で9名減った(男子が8名減)こと以外では、ほぼ例年と同じような結果となっています。
上表でご紹介していない中学校の合格・進学状況を簡単にご紹介しておきましょう。広島国際学院中の合格者は男子14名、女子3名で、進学者は男子3名、女子1名です。広島協創中の合格者は男子1名、女子7名で、進学者は男子1名、女子2名です。山陽女学園中等部の合格者は5名で、進学者は2名です。受験者の少ない中学校については割愛させていただきます。また、県外の中学校については、まだ確認を終えていませんので掲載できません。
主要私立男子校の合格状況と進路の選択状況
広島学院の合格者数は昨年とほぼ同じでしたが、進路として選択した受験生は昨年よりも多く、45名でした。これは、広島大学附属との重複合格者の多くが広島学院を進路として選択していることによるものと思われます。修道の合格者数は147名でした。これは昨年並みで、進路として選んだ受験生の数も昨年とほぼ同じで、3月2日現在の進学予定者数は83名です。広島城北への進学者は、昨年の20数名から36名に回復しています。
なお、広島の男子私学最高峰の広島学院に合格したものの、他校を進路として選択した受験生ですが、その内訳は修道2名、広島城北1名、広島なぎさ1名、広島国際学院1名、広島大学附属1名、県立広島1名、市立広島中等教育3名、進路未確認2名でした。広島学院に合格して他校に進学する場合、例年なら大概は附属か修道なのですが、今年はいろいろですね。特に市立広島中等教育への3名には驚かされました。
主要私立女子校の合格状況と進路の選択状況
前述のように、ノートルダム清心の合格者が85名と大幅に増加し、進路として選択した受験生の数も、昨年の52名に対して63名と増加しています。広島女学院の合格者は145名で、昨年の147名とほぼ同じ数の合格者を輩出しました。ただし、進路として選んだ受験生の数は、3月2日現在で52名と、昨年の67名よりもかなり少なくなっています。ただし、同校の合格者で進路が未確認になっている受験生が若干名いますので、もう少し増えるかもしれません。安田女子の合格者も昨年とほぼ同じでしたが、進路として選択した受験生は昨年比で若干減少しています。これも進路が未確認の受験生がいますので、昨年とあまり変わらない数に落ち着くかもしれません。
広島の女子私学最高峰のノートルダム清心に合格したものの、他校を進路として選択した受験生の内訳ですが、広島女学院1名、広島大学附属8名、広島大学附属東雲1名、県立広島5名、市立広島中等教育3名、進路未確認4名でした。やはり、女子の場合は共学志向が男子よりも強く、国公立の共学一貫校を選択する比率が随分高いようです。
以上、今年の弊社会員受験生の合格状況と進路選択状況を簡単にご紹介してみました。広島の中学受験対象校のスタンダードと言えば、男子私学の修道、女子私学の広島女学院です。これらの私学への弊社会員の合格状況を見ると、かつてよりも大幅に合格を巡る競争は緩和され、「弊社の教室に通い、普通に受験勉強に取り組んでいれば合格できる」という状況が訪れているように思います。
しかしながら、このような入試の実態に鑑みるなら、中学進学後の学業面の見通しをしっかりと立てながら受験準備をすることの重要性に気付かされるでしょう。中途半端な受験勉強でも受かる可能性がありますが、そんな勉強で進学すると後で苦労するのは必定です。児童期は、ものごとに取り組む姿勢を築くうえでも大切な時期です。生活面も勉強面もどれだけ自立できているかが後々まで影響します。人間としての特性が定まった中学生になってからでは変わろうにも変わることができません。また、「勉強はもうこりごりだ」といったような猛勉強も、「労多くしてなんとやら…」で、子どもの将来に暗い影を落としがちです。勉強に向かう志向性がなし崩し的に失われてしまうと、中高一貫校でのがんばりや飛躍が期待できなくなってしまいます。子どもたちにはこれから長い人生が待ち受けています。そのことをよく踏まえた受験生活を送っていただきたいですね。
昨秋、修道の校長先生にオンラインの催しで弊社会員に向けたお話しをしていただいた際、「ハビトゥス」の重要性について言及しておられました。ハビトゥスとは、ラテン語に由来する言葉で、「長い期間にわたって繰り返された行動によって、無意識のレベルにまで浸透した習慣や行動の構え」といったような意味をもちます。勉強を例にたとえると、「決めた勉強を決めた時間にやるのが当たり前になり、やらないままにしてしまうことが許せない、やらずにはいられない」といった具合に、ごく当たり前のこととして習慣化しておくことが大切だという意味でおっしゃったのだと思います。
志望校に進学する夢が叶えば、あとが保障されるということは決してありません。受かったあとも変わりなく精力的に学び続けることが将来につながるのは疑いようがありません。「何が何でも合格」という猛勉強をしなくても受かるのですから、「合格後」を見据えた受験生活を送る余裕があります。その余裕を生かす意味においても、受験生活を通してハビトゥスを形成していくような受験生活をこれからの中学受験生には送っていただきたいですね。
先週の土曜日、弊社の新年度講座が開講しました。今から受験に備えた勉強をするにあたっても、上記のようなことを踏まえ、収穫の多い受験生活を送っていただきたいと切に願っています。また、弊社にご縁をいただいていないご家庭におきましても、今回の記事が多少なりとも参考になれば幸いです。
カテゴリー: お知らせ, アドバイス, 中学受験, 勉強について, 家庭学習研究社の理念
2023 年 2 月 18 日
中学入試が終わり、弊社会員の合格者や進路選択の状況がほぼ判明しつつあります。そこで今回は、弊社会員の公立一貫校受検状況と、合格者数、進路としての選択状況をお伝えしようと思います。なお、資料はあくまで参考としてお知らせするものです。会員家庭から提出していただいた報告書をもとに作成していますので、絶対的なものではありません(まだ未提出の家庭が若干あります)。
とりあえず、弊社会員の主要な受検対象である広島県立広島中学校と広島市立広島中等教育学校の受検状況と合格・進学の様子はあらかた掌握できていますので、この2校についてご紹介してみましょう。
主要公立一貫校の受検状況と弊社会員の合格・進学状況 (2/24 現在)
|
学校名
|
定員
|
志願者
|
弊社受検者
|
弊社合格者
|
弊社進学者
|
|
県立広島中学校
|
160
|
638
|
男子27
|
57
|
男子11
|
34
|
男子8
|
24
|
|
女子30
|
女子23
|
女子16
|
|
市立広島中等教育学校
|
120
|
354
|
男子19
|
38
|
男子11
|
27
|
男子7
|
17
|
|
女子19
|
女子16
|
女子10
|
※県立叡智学園中学校の合格者は3名、進学者は2名です。
公立一貫校は、基本的に合格発表時は定員数通りに合格者を公表します。したがって上記2校共にかなりの倍率であり、一定期間のきちんとした受検対策なしには受かりません。これまで県立広島中学校も市立広島中等教育学校も、弊社会員の受検状況を見るかぎり男子よりも女子の進学対象校として人気が高く、女子の受検者が男子よりもかなり多い現象が続いていました。これは複数の子どものいる家庭の経済的な負担や、女子の共学志向が高いことなどが主な原因と考えられます。
ただし、県立広島は平成16年の開校当初から「ことば科(中学課程)」などの教育実践が評価されるとともに、大学への進学実績も良好なことから、最近では弊社においても男子の受検者・合格者の比率が高くなり、実際に受かった場合にも進路として選択するケースが増えています。
市立広島中等教育のほうは、弊社会員においては女子のほうに人気が偏り、弊社の男子は受かっても進路として選択されるケースが少なかったのですが、今年に関してはかなりの数の合格者が進路として選択しています。その理由はまだ掌握していませんが、同校は熱心な教育実践で入学者の満足度も高く、男子受験生の人気が高まったとしても不思議ではありません。
① 県立広島中学校
 弊社からの受検者の校舎別の内訳を見ると、地元の東広島校からの受検者が最も多く、僅差で広島校から多く受検しています。最近は呉校からの受検者も増えており、合格者も5名出ています。その他の校舎からの受検者は男女とも少数でした。なお、弊社の場合は基本的に広島の有力私学への進学指導が中心となっていますが、県立広島は上述のように東広島市および周辺地域以外のJR沿線に住まいのある家庭のお子さんの受検が徐々に増えています。私学受験に対応する十分な基礎学力をつけたうえで公立一貫校対策の指導を受けた子どもたちの学力は総じて高く、ノートルダム清心や広島女学院との重複合格者が多数います。県立広島に進学したら、大学受験までの6年間でやることは基本的に同じですから、これまで培ってきた確かな基礎学力が大いに威力を発揮することでしょう。
弊社からの受検者の校舎別の内訳を見ると、地元の東広島校からの受検者が最も多く、僅差で広島校から多く受検しています。最近は呉校からの受検者も増えており、合格者も5名出ています。その他の校舎からの受検者は男女とも少数でした。なお、弊社の場合は基本的に広島の有力私学への進学指導が中心となっていますが、県立広島は上述のように東広島市および周辺地域以外のJR沿線に住まいのある家庭のお子さんの受検が徐々に増えています。私学受験に対応する十分な基礎学力をつけたうえで公立一貫校対策の指導を受けた子どもたちの学力は総じて高く、ノートルダム清心や広島女学院との重複合格者が多数います。県立広島に進学したら、大学受験までの6年間でやることは基本的に同じですから、これまで培ってきた確かな基礎学力が大いに威力を発揮することでしょう。
なお、県立広島に合格したものの、他校を進路に選んだ受験生の進路はつぎのとおりです。男子は、修道1名、国際学院1名(このお子さんは広島学院・修道にも合格)、広島中等教育1名でした。女子は、ノートルダム清心4名、広島女学院1名、広島大学附属1名でした。合格者のうち1名は、まだ進路が判明していません。
②広島中等教育学校
 広島中等教育学校は、安佐北区の山間の団地に位置するため、交通手段がバスに限られます。しかも市の中心部から遠いため、弊社会員の場合、三篠校と広島校会員の受検がほとんどです。男子の場合、これらの学区の受験生の最もポピュラーな進学対象校は修道であり、多くの受験生が修道との併願でした。したがって、修道に受かったら大半が修道を選択するのが一般的でした。しかし、今年は男子合格者の歩留まりがかつてないほどほどよく、合格者11名中7名が同校に進学する模様です。
広島中等教育学校は、安佐北区の山間の団地に位置するため、交通手段がバスに限られます。しかも市の中心部から遠いため、弊社会員の場合、三篠校と広島校会員の受検がほとんどです。男子の場合、これらの学区の受験生の最もポピュラーな進学対象校は修道であり、多くの受験生が修道との併願でした。したがって、修道に受かったら大半が修道を選択するのが一般的でした。しかし、今年は男子合格者の歩留まりがかつてないほどほどよく、合格者11名中7名が同校に進学する模様です。
広島中等教育学校は、立地条件ゆえ県立広島ほど多くの受験生を集めていませんが、それでも実質倍率はかなり高く、簡単には受からない学校となっています。弊社の合格者を見ても、かなり高い学力を有している子どもたちでした。今年は特にその傾向が強く、たとえば男子の場合、広島学院や修道との併願ですべて合格した受験生もおり、そのなかには進路としても同校を選択している例もあります。
ついでながら、広島中等教育学校は「山間の奥まった場所にある」というイメージが強く、そのため受験生の居住地が安佐北区や安佐南区などに偏っています。ですが、バスの便は結構多く、多少は遠くても進学する価値のあるよい学校だと思います。筆者は同校の近隣に居住していますが、見かける生徒さんの立ち居振る舞いは好ましく、勉学にしっかりと向き合っているという印象があります。通学にかかる時間を調べ、この学校を受験候補の一つにあげてみてはいかがでしょうか。
なお、広島中等教育学校に合格したものの、重複合格した他校を進路に選んだ受験生はつぎの通りです。男子は、広島学院2名、修道1名でした。女子は、ノートルダム清心3名、広島大学附属2名でした。女子合格者のうち2名は、まだ進路が確認されていません。
上述のように、弊社は広島の伝統的私学4校(学院・修道・清心・女学院)への進学指導を軸に置いた指導をしていますが、近年は公立一貫校への進学希望者が相当数あり、公立一貫校対策の指導にも力を入れています。6年生の4月末までの「基礎力養成期」の指導は悉皆で行っており、「応用力養成期」に入ってから希望者を対象に公立一貫校対策の指導をしています。私立の有力校に行く受験生と遜色ない基礎学力をつけておけば、公立一貫校に入ってからも学力面で大いに飛躍が期待できるでしょう。また、大学受験で求められる学力はどんな形態の中学高校を経由しても一緒ですから、なおさら基礎を固めておくことが有効に作用すると確信しています。
この記事が来年以後の受験生家庭の参考になれば幸いです。
カテゴリー: がんばる子どもたち, アドバイス, 中学受験, 家庭学習研究社の特徴, 家庭学習研究社の理念
2023 年 2 月 10 日
今回は、前回お伝えしたことの続きを書いてみようと思います。これから学習塾選びをされるご家庭の保護者だけでなく、新年度の会員として通学を予定されているお子さんの保護者にもぜひ読んでいただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
前回、受験のプロセスで身につけはるべきは入試を突破できるテスト学力だけでは不十分で、志望校進学後の教育環境の下で有意義な学校生活を送り、学業面で飛躍を遂げるうえで欠かせない資質を身につけることが重要だといったような趣旨のことをお伝えしました。それが何かについては、前回のブログで「お子さんは、こんな問題を抱えていませんか?」という問いかけで例示した、10項目の表現を裏返しにしてみるとおわかりいただけることでしょう。
児童期までに身につけておきたい習慣や姿勢
1.学校の宿題は、早めに(帰宅後夕食ま
でに)済ませる(※塾のない日)。
2.計画的な学習の習慣を身につける。
3.遊びと勉強の切り替えができる。
(勉強の時間になったら机に着く)
4.何事も、決めたことは最後までやり
遂げようと努力をする。
5.やるべきことの優先順位をつけ、重要事項を後回しにしない。
6.朝の起床をはじめ、自分のことは自分でやれる。
7.失敗をしたら理由を振り返り、同じ失敗をしないようにする。
8.自分のしたことを客観的に評価できる(ある程度自分に厳しい)。
9.何事につけ、先を見通して行動する姿勢を身につける。
10.仲間と励まし合ったり競い合ったりすることに熱心である。
上記の10項目は、受験学力を身につけるうえで必須ではないかもしれません。テスト学力は大人の指示やサポートで補えるからです。しかしながら、中学や高校に進学したらもはや大人の力を借りることはできません。何につけても自分で判断して行動する自律性が問われるようになります。この行動の自律性は、一朝一夕には備わりません。また、自我が確立する児童期までに身につけておくべきものです。それをおざなりにすると、何をするにつけても自律的行動の欠落が足を引っ張り、一生自らの抱える問題として尾を引くことになりがちです。当面危ぶまれるのは学業面での飛躍ですが、学業で後れを取った後の挽回がいかに難しいかは、前回お伝えしたとおりです。
ですから、中学受験をめざすなら、「学力+行動の自律性」の獲得を目標に掲げた受験生活を送るべきではないでしょうか。言わずもがなですが、児童期は子育ての重要な時期にあたります。子どもの自律性を育むことは親としての重要な仕事の一つです。勉強の見守りと同じぐらい、あるいはそれ以上に子どもの内面の成熟・成長を大切にしていただきたいものですね。ただし子どもの内面の成長曲線は一人ひとりみな違います。なかには親の期待通りに成長しないお子さんもいることでしょう。ですが、そこで業を煮やして無理矢理勉強させても子どもの自律は遅くなるばかりです。そしてそのつけは子ども自身が先々の苦労という形で払わされることになってしまいます。
残念ながら、自律と学力形成の両方を大切にした受験生活は、親子が望む最高の受験結果をもたらしてくれるとは限りません。それでも、自律に向けた成長の流れはたとえゆっくりでも決して無駄になりません。どの中学校に進学したとしても、内面の成長が追い付き始めたなら、徐々に好循環の連鎖が子どもの背中を押してくれるようになります。やるべきことを自分で判断し、それが少しずつできるようになってくるのです。人生の見通しは、概ね社会への参入後に定まっていきますが、自律に向けて努力を怠らなかった人は、この段階で確かな手応えをもてるようになっていくことでしょう。これこそががはるかに重要だと思います。
ここで、新年度の講座の開始段階から当分の間保護者にお願いしたい見守りと応援のスタンスをお伝えしてみようと思います。
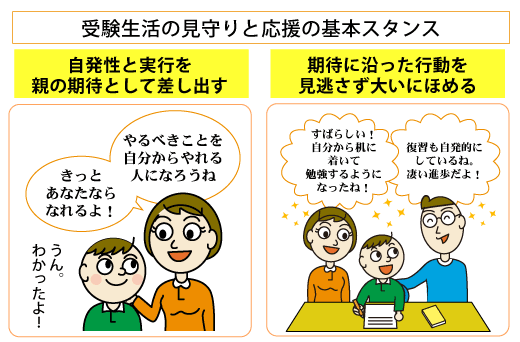
・会員家庭には、必ず学習の計画表を作成していただきます。親が決
めるのではなく、一緒に考えながら子どもが実行可能な計画になる
よううまくサポートすると実行が伴います。
・当面は、行動の自己管理と自発性を評価軸に応援してあげてくださ
い。計画通りやれたら、すかさずほめてあげてください(親の評価
がまだ一番意欲に影響する年齢です)。努力を評価軸に!
・生活上、自分のことは自分でやる習慣が、行動の自律のベースにな
ります。行動の主体性も、生活習慣の自立から生まれます。
・4・5年生は、子どもの学習状況を保護者が掌握することが必要で
す。「難しいことをやっているんだね。がんばって!」と、応援し
てやりましょう(4年は、取り組んだ問題の〇つけもお願いしてい
ます)。
・2週間に1度のテスト(マナビーテスト)が終わったら、ベストを
尽くせたかどうかを親子で振り返りましょう。
・成績が悪かったときこそ、親の関わりが問われます。
叱るのではなく、「どこがいけなかったのかな?」と反省点を考え
させたり、一緒に悔しがったりすれば子どもは素直に反省します。
開講後の学習(授業や家庭学習)について、詳しくは配布資料等でお伝えします。どんな指導を受けているのか、親はどう関わるべきかについて、保護者がしっかりと把握されていれば、自然とお子さんの勉強への関わりも妥当なものになります。
未完成な小学生の受験ですから、親は心配や骨折りの毎日になりがちです。しかし、親の関わりが子どもを自律へと向かわせるものであれば、段々と親の負担は少なくなっていきます。逆に、あれもこれもと親が手を貸せば、受験が近づくほどに親の苦労は増え続けていきます。子どもの内面の成長を期待しつつ、適切な間合い、すなわち「つかず離れず」の見守りと応援をお願いしたいと存じます。そうすれば、やがてお子さんは受験での合格に求められる学力を自らの力で養うとともに、自分を適切に律する姿勢も身につけられることでしょう。
以上のような考えに基づく受験生活で、志望校合格の夢が叶えられるよう応援してあげてください。このような受験なら、その結果がいちばん希望したものにならなかったとしても、お子さんの将来は前途洋洋です。自律こそ、人間として成功するための一大条件なのですから。
弊社の教室で学び、受験をめざしてみませんか? 入会をお待ちしています!
カテゴリー: がんばる子どもたち, アドバイス, 中学受験, 入塾について, 勉強について, 子どもの自立, 家庭学習研究社の理念
 弊社からの受検者の校舎別の内訳を見ると、地元の東広島校からの受検者が最も多く、僅差で広島校から多く受検しています。最近は呉校からの受検者も増えており、合格者も5名出ています。その他の校舎からの受検者は男女とも少数でした。なお、弊社の場合は基本的に広島の有力私学への進学指導が中心となっていますが、県立広島は上述のように東広島市および周辺地域以外のJR沿線に住まいのある家庭のお子さんの受検が徐々に増えています。私学受験に対応する十分な基礎学力をつけたうえで公立一貫校対策の指導を受けた子どもたちの学力は総じて高く、ノートルダム清心や広島女学院との重複合格者が多数います。県立広島に進学したら、大学受験までの6年間でやることは基本的に同じですから、これまで培ってきた確かな基礎学力が大いに威力を発揮することでしょう。
弊社からの受検者の校舎別の内訳を見ると、地元の東広島校からの受検者が最も多く、僅差で広島校から多く受検しています。最近は呉校からの受検者も増えており、合格者も5名出ています。その他の校舎からの受検者は男女とも少数でした。なお、弊社の場合は基本的に広島の有力私学への進学指導が中心となっていますが、県立広島は上述のように東広島市および周辺地域以外のJR沿線に住まいのある家庭のお子さんの受検が徐々に増えています。私学受験に対応する十分な基礎学力をつけたうえで公立一貫校対策の指導を受けた子どもたちの学力は総じて高く、ノートルダム清心や広島女学院との重複合格者が多数います。県立広島に進学したら、大学受験までの6年間でやることは基本的に同じですから、これまで培ってきた確かな基礎学力が大いに威力を発揮することでしょう。
 広島中等教育学校は、安佐北区の山間の団地に位置するため、交通手段がバスに限られます。しかも市の中心部から遠いため、弊社会員の場合、三篠校と広島校会員の受検がほとんどです。男子の場合、これらの学区の受験生の最もポピュラーな進学対象校は修道であり、多くの受験生が修道との併願でした。したがって、修道に受かったら大半が修道を選択するのが一般的でした。しかし、今年は男子合格者の歩留まりがかつてないほどほどよく、合格者11名中7名が同校に進学する模様です。
広島中等教育学校は、安佐北区の山間の団地に位置するため、交通手段がバスに限られます。しかも市の中心部から遠いため、弊社会員の場合、三篠校と広島校会員の受検がほとんどです。男子の場合、これらの学区の受験生の最もポピュラーな進学対象校は修道であり、多くの受験生が修道との併願でした。したがって、修道に受かったら大半が修道を選択するのが一般的でした。しかし、今年は男子合格者の歩留まりがかつてないほどほどよく、合格者11名中7名が同校に進学する模様です。

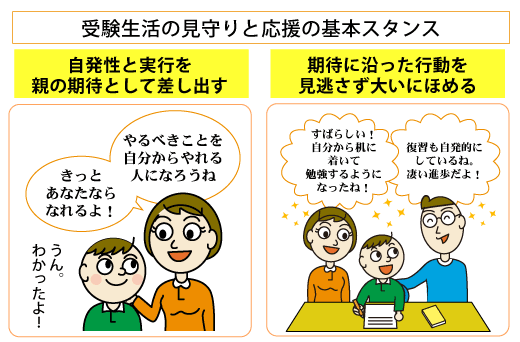
 このページは
このページは